婚礼エージェントは生き残れるか?
現役ブライダル企業 部長 CHIKARA
2019.03.02
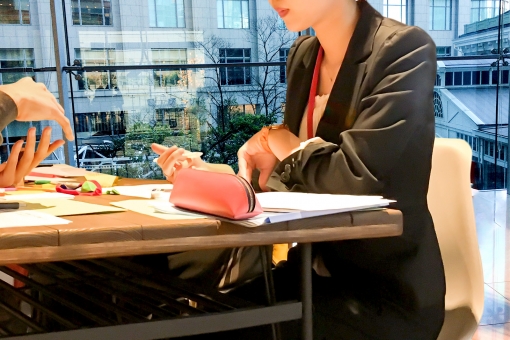
婚礼エージェントという言葉を聞いたことがありますか?
業界の構造について少しご説明をします。
そもそも婚礼エージェントって何?
今や結婚が決まったカップルが結婚式場を探す際に手に取るのが、ゼクシィやインターネットの情報ではないでしょうか。
手軽に利用でき、費用もそれほど掛からない。
欲しい情報が手に入り、欠かせないアイテムですよね。
しかしそうした 媒体が無かった時代、人々が利用したのが「婚礼エージェント」でした。
婚活エージェントって何?ってな感じで、一般的には馴染みが浅く、何のことか知らない人も多いことでしょう。
「婚礼エージェント」はカップルに対して結婚式場を見つける手伝いを無料で行い、紹介した婚礼施設からお金を貰うというビジネスなのです。
婚礼エージェントの歴史は古く、発祥は1980年代にまで遡ります。
当時はまだインターネットもゼクシィもなかったので、カップルは結婚が決まってもどのように情報を集めればよいのかが分かりませんでした。
それで、百貨店等に「無料相談コーナー」が設けられ、相談員(大抵は年配の女性)が相談に乗ってくれるサービスを行ったのでした。

婚礼エージェントは、カップルの式の希望を聞いて「それなら、ここと、ここを見に行ってご覧なさい」と大きな封筒に入ったパンフレット類を渡してくれ、予約も取ってくれるという親切さでした。
二人が施設見学に行き、式場が決定すると、エージェントは披露宴における料理・飲食費用の15%から20%を施設に請求する、という仕組みなのです。
料理・飲食といえば、1人20000円はするわけで、その20%なら例えば70人だと、20,000×0.2×70=¥280,000
え?結構大きくないですか?
最初に相談に来た時にまとめて5箇所くらい紹介しておけば、どこかでは決まるでしょう。
そしてそこから28万円が入ってくる。
なかなか素敵なビジネスですね。
- 昔は「婚活エージェント」が存在し、式場探しを行っていた
なかなか上手いアイデアの婚礼エージェント

「婚礼エージェント」ビジネスはまさしく時代のニーズをついていたといえるでしょう。
式場にしてみたら、この「婚礼エージェント」のスタッフに気に入られないと、お客候補である新郎新婦を紹介してもらえないのです。
そうした理由で婚礼担当者は足しげく菓子折りなどを持って相談所に通っていたそうです。
また婚礼エージェントにはカップルを紹介してもらうだけでなく
そうしたカップルの希望や傾向、ニーズなどの有益な情報が多く集まる為に、式場にとっても大変価値のあるものとされていたそうです。
ただ、当時は手作業ですから、お客様を「紐付き」にするために証拠を残すことが大変でした。
悪い考えですが、式場側が「お客様来られたけど、決まりませんでした」と言ってしまえば、28万は払わないで済むのです。
実際その時には決まらず、後になってカップルが思い返して決まったような時はどうするのか。
また2箇所のエージェントから紹介があった場合、どちらを優先するのか。
電話はA社が先だったが、来た二人はB社の紹介状を持ってきた、とか…。
このようなトラブルも結構あったようです。

そして、「婚礼エージェントビジネス」への参入企業がドンドン増えたのでした。
百貨店だけでなく、スーパー、商業ビル内などに様々な名前で出店がされました。
また衣裳屋など資金力のある婚礼企業が、エージェント業も行うケースが出ました。
衣裳屋は式場紹介だけではなく、新郎新婦に対し、自社の衣裳も提案できるので、一挙両得と言えるわけです。
しかも衣裳を提供する際、式場を通さないため、手数料を払う必要がなく、利益率がとても高くなります。
逆に、衣裳屋に持ち込みをされると、式場側は自社専属の衣裳屋の衣裳が売れず、手数料が入ってきません。
しかも、ビジネスチャンスを失った衣裳屋からは当然文句を言われます。
「年間何百組も発注がいただけるということで、敷金も払ってホテル内に衣裳室や事務所を構えて、毎月家賃を払っているのに、なんでそんな持ち込みを許すんですか?」って、当然ですよね。
エージェントに決定的な打撃を与えたのはゼクシィの登場でした。
読者が自分で見学先を探し始め、様々な情報を入手できるようになったため、エージェントの必要性が薄まったのです。
- 百貨店や、スーパー等様々な場所で婚礼エージェントによる式場紹介が行われた
エージェントもwebビジネスへ移行

エージェントは今も昔も変わらず存在します。
「結婚式の準備の仕方が分からない」
「何から準備を進めればいいか分からない」
そんな新郎新婦の為にエージェントが存在するのです。
情報集めには役立つかもしれません。
ただ、インターネットで簡単に情報が集められるようになると、エージェント業は厳しくなって来ました。
それに世の中が紹介料の仕組みを知ってしまうと、昔ほどありがた味がなくなって来ました。
組数を稼ぎたい式場は、値下げで新規を獲得しようとしていますから、これ以上紹介料を払うと命取りになり兼ねません。
エージェント手数料の最適化も求められますし、持ち込みの制限も出てきました。
それ以上にエージェントが林立し、競争が激しくなったことも事実です。
例えば対面でなく、オンラインで二人の相談に乗ってあげるとか
見学に行った後、見積もりに対してアドバイスをあげるとか、
ネットを使ってのサポートやデータ提供、
また本当に中立の立場で二人の味方になってあげるなど、新しい手法が必要ですね。
それが実現すれば、また新しいスタイルのエージェントも盛んになるのではないでしょうか。
その後も競合が増え、トラブルも起こり、経営はなかなか厳しくなるばかり。
存続の顧望はIT化にある。
AIなどをしようして、本当にカップルにが求めているデータを提供できるような「新エージェント」が登場すればまたマーケットは変わるだろう。





